女性の健康週間
女性の健康週間とは
女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援するものです。
国及び地方公共団体等では、女性が自らの健康に目を向け、自らが健康づくりを実践できるよう支援する、女性の健康づくりに取り組んでいます。
期間
毎年3月1日~8日までで
(3月8日は国際女性デー)
令和6年度のテーマ
「女性の健康を支える地域・社会の役割~誰一人取り残さない健康づくりの実現に向けて~」
▼令和6年度 女性の健康週間を記念してイベントが開催されます。
- 厚生労働省スマートライフプロジェクト「令和6年度女性の健康週間特設ページ」
女性の健康課題とは
女性特有の健康課題についてはあまり着目されておらず、健康日本21(第二次)では性差を考慮した取り組みが少ない状態でした。
しかし、2024年4月から始まった健康日本21(第三次)では、女性はライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性等を踏まえ、「女性の健康」を新たに項目に追加しました。
そして、女性に多いやせ、骨粗鬆症等の健康課題、男性とは異なる傾向にある女性の飲酒及び妊婦に関する目標を設定しています。
| 目標 | 指標 | 目標値 |
|---|---|---|
| 若年女性のやせの減少 |
BMI18.5未満の20歳~30歳代女性の割合 |
15%(令和14年度) |
| 骨粗鬆症検診受診率の向上 | 骨粗鬆症検診受診率 | 15%(令和14年度) |
|
生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒している女性の減少 |
1日当たりの純アルコール摂取量が20g以上の女性の割合 | 6.4%(令和14年度) |
| 妊娠中の喫煙をなくす | 妊婦の喫煙率 |
第2次成育医療等基本方針に合わせて設定 |
女性の飲酒
女性は男性よりも飲酒の影響を受けやすい
女性は特有の飲酒リスクがあります。
- 血中アルコール濃度が高くなりやすい
- 乳がんや胎児性アルコール症候群などの女性特有の疾患のリスクを増大させる
- 早期に肝硬変やアルコール依存症になりやすい
健康日本21(第三次)においても、生活習慣病リスクを高める飲酒量を1日の純アルコール摂取量が男性 40g以上、女性 20g以上と定められています。
多気町では約1.3%の女性が生活習慣病を高める量を飲酒しています。
女性にとっての適量は、男性よりも少量です。
妊娠中・授乳期は飲酒を避けて
妊娠中・授乳期に飲酒をすると、妊娠中は胎盤を通して胎児に、授乳期は母乳を通して赤ちゃんにアルコールが運ばれてしまいます。アルコールは胎児・乳児の脳や発育に悪影響を及ぼす危険性があります。
妊娠したとわかったら、禁酒をしましょう。
▼女性と飲酒について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
妊娠している女性の周りも禁煙しよう
女性は受動喫煙の機会が多い
女性の喫煙率は男性に比べて低くなっています。多気町の令和6年(2024年)度調査では、男性20.0%、女性3.9%でした。年齢階級別にみると、女性は60歳代が最多で7.4%となっており、次いで10₋20歳代、40歳代の4.5%と続きます。
国内では家庭で受動喫煙の機会が「ほぼ毎日」あった人は、男性7.4%、女性11.6%と女性に多く、受動喫煙による妊娠出産への悪影響の回避が課題となっています。
妊婦・胎児への影響
妊娠への影響
喫煙は妊娠にも以下の影響を与え、妊娠しづらくなってしまいます。
- 避妊をやめてから妊娠するまでの期間が長くなる
- 閉経が早まる
妊婦・胎児への影響
妊婦本人・周囲の喫煙は、妊娠・出産の過程において、さまざまな健康影響を及ぼします。
- 早産や低出生体重・胎児発育遅延のリスクを高める
- 乳幼児突然死症候群/SIDSのリスクを高める
- 子宮外妊娠、常位胎盤早期剥離、前置胎盤を引き起こす可能性
妊婦の受動喫煙によってもこれらのリスクが高まることが指摘されています。
▼女性と喫煙の関係について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
- 厚生労働省e-ヘルスネット「女性の喫煙・受動喫煙の状況と妊娠出産への影響」
骨活のすすめ
「骨粗しょう症」と聞くと高齢者がなる病気だと思う方も多いかもしれませんが、実は若い女性であっても、栄養不足、月経不順、運動不足などによって、骨密度が低下して骨粗しょう症を発症したり、骨折してしまう可能性もあります。
骨粗しょう症の予防には、バランスの良い食事や適度な運動が効果的です。
骨を丈夫にするためにはカルシウムの摂取が大切ですが、他にカルシウムの吸収を促進するビタミンD、骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミンKなど、様々な栄養素も必要です。エネルギーと栄養素をバランスよくとることが大切です。また、ビタミンDは、紫外線を浴びることで体内でつくられます。
また、骨は負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり強くなります。そのため、 散歩したり、階段を使ったりするなど、日常生活のなかでできるだけ体を動かすようにしましょう。
▼多気町では、40~69歳の女性の方を対象に骨粗しょう症予防検診を実施しています。詳細はこちらをご確認ください。
▼予防のための取り組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- 厚生労働省eヘルスネット「骨粗鬆症の予防のための食生活」
- 厚生労働省eヘルスネット「骨粗鬆症予防のための運動 -骨に刺激が加わる運動を」
自分のからだと適正体重の大切さ
ご自分の体型について、どのように感じていますか?
国際的に、太っている・やせているの度合いは、BMIと呼ばれる指標で判断します。BMIはボディマス指数と呼ばれ、体重と身長から算出される肥満度を表す体格指数です。
日本肥満学会では、BMIが22を適正体重(標準体重)としており、統計的に最も病気になりにくい体重とされています。25以上を肥満、18.5未満を低体重としています。
自分の肥満度・やせ度合いを計算してみましょう。
BMIの計算方法は、体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))です。
(例)身長160cm、体重60kgの場合のBMI:60kg×(1.6m×1.6m)=23.4
また、自分の適正体重はどれくらいかを知る計算方法は、身長(m)×身長(m)×22です。
(例)身長160cmの場合の標準体重:1.6m×1.6m×22=56.3kg
現在の体重が標準体重より少ない場合は、食事をきちんと取ることを意識しましょう。多い場合でも、無理なダイエットは禁物です。
▼日本医師会のホームページから、自分のBMIや適正体重を計算してみましょう。
https://www.med.or.jp/forest/health/eat/11.html
「やせ」に気を付けて
やせている方が素敵に見えるかもしれませんが、実は「やせ」は身体にとって大きな影響を及ぼしてしまいます。
例えば・・・
- 栄養不足による貧血、疲れやすい
- 風邪などの感染症になりやすい
- 身体の成長への影響
- 月経不順
- 低出生体重児出産のリスク
さらに、やせのまま年齢を重ねると、筋肉量の低下によるサルコペニア(筋肉減少症)、骨量の低下による骨粗しょう症になる危険があり、転倒・骨折から要介護へつながる恐れもあります。
BMIが「やせ」であった方は、自分の身体のため、バランスの良い食事や適度な運動を行い、健康的な体型を目指しましょう。
参考
- 厚生労働省ホームページ 「女性の健康づくり」
- 厚生労働省「女性の健康推進室ヘルスラボ」
- 厚生労働省スマートライフプロジェクト「令和6年度 女性の健康週間特設ページ」
- 厚生労働省 スマートライフプロジェクト 「骨活のすすめ」
- 厚生労働省 スマートライフプロジェクト 「すこやかなカラダのためにできること」(適正体重の大切さ)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康増進係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム


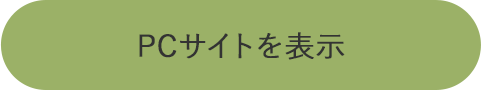
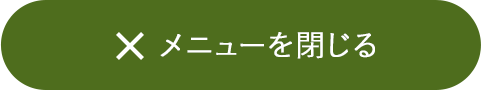
更新日:2025年02月28日