町内指定文化財一覧【町指定文化財】
54件(2024年4月現在)
18 木造大日如来坐像(もくぞうだいにちにょらいざぞう)
所在地:長谷 近長谷寺
年代:平安時代
指定:平成元年12月15日

像高94.5センチメートル檜材の一木造り。総体的に痩せ身で、面相、体躯ともに繊細な彫技で一貫している。
19 三摩耶戒儀(さんまやかいぎ)
所在地:多気郷土資料館(相可 浄光院より寄託)
年代:室町時代
指定:平成元年12月15日

三摩耶戒儀とは、密教で仏門に入る者や昇進者の頭上に香水をそそぐ灌頂の儀式前に行われる三摩耶戒の式次第である。町内における中世の貴重な書跡である。永正11年(1514)、僧永盛により筆写された。
20 山門(法泉寺)(さんもん(ほうせんじ))
所在地:相可
年代:江戸時代
指定:平成元年12月15日

黄檗宗の名刹であった旧法泉寺の山門。高さ7.7メートル、幅11メートル、中国風で黄檗宗独特の建築様式である。中央上部に開山梅嶺和尚の筆による「天照山」の横額がかかっている。
21、伝銅鐸出土地(でんどうたくしゅつどち)
所在地:四疋田
年代:
指定:平成元年12月15日

昭和19年10月頃、東池下の丹生寺(ニュウジ)より出土したと伝えられるが、出土した銅鐸の文様、現在の所在地など全く不明である。
22 薬種商看板(やくしゅしょうかんばん)
所在地:西池上
年代:江戸時代
指定:平成元年12月15日

高さ1.97メートル、幅58センチメートル。ケヤキ製で、上方に唐破風つきの屋根がある。薬種商金粒丸本舗大好庵の所有であったが、明治の末、西村家に移された。看板の文字「きんりうくはん」は儒家三谷蒼山の筆と伝えられる。
23 大楠(おおくす)
所在地:前村
年代:
指定:平成元年12月15日

樹齢は推定およそ600年、幹周7.5メートル、の巨木である。この一帯は北畠氏および南朝派一族の隠遁地であったといわれている。その遺蹟を後世に伝えるために一老樹を保存して、記念の表徴としてきた。時を経て、地区民はこれを神木と仰ぎ、根元に小祠を祀り保存している。
24 伊勢椿の原木(いせつばきのげんぼく)
所在地:丹生 丹生神社境内
年代:
指定:平成6年3月29日

元周囲は49センチメートル・67センチメートル・75センチメートル 樹高は4.5メートルの三本の椿からなっている。『勢国見聞集15巻』、名木之部に「丹生の椿丹生村大明神の社内、嵯峨天皇の御宇に植しなり」と記されている。なお、『丹洞夜話』や『勢陽五鈴遺響』、『三重県植物誌』にも紹介されている。
25 長龍神事(ちょうろうしんじ)
所在地:片野
年代:室町時代
指定:平成6年3月29日

永生16年(1519)に始まり、毎年正月に片野八柱神社境内において長龍舞楽を行っていたが、現在は春分の日に行っている。片野神社には出雲系の神様が祀ってあり、ここで演じられる「長龍」は須佐之男命が出雲の国において八岐大蛇を退治した神話を象徴化したものである。須佐之男命にみたてた赤天狗とその妻黒天狗が協力して八岐大蛇を退治する勇壮な舞楽である。
26 丹生暦の版木(にゅうごよみのはんぎ)
所在地:勢和資料館
年代:江戸時代
指定:平成6年3月29日

縦32.5センチメートル、横13.5センチメートル、桜材で作られた柱暦の版木である。近世を通じて伊勢の国を中心に出回っていた暦は、丹生に在住して代々賀茂杉大夫と称していた暦師が独占して発行していた。この版木は弘化2年(1845)毎月の主な暦象が簡略に記され、家の柱に貼ったことから柱暦と言われているものである。
27 銀象眼太刀(ぎんぞうがんたち)
所在地:多気郷土資料館
年代:古墳時代
指定:平成6年8月1日

長さ約71センチメートル、幅約3センチメートル。平成4年に当町荒蒔の石塚谷古墳(6世紀後半)から出土した。銀象眼によって、刀身の両面に先端から順に、魚・鳥・日輪(太陽)の文様が施されている。これらは古代中国に由来する吉祥文とされる。3種類の文様が揃っているのは全国的にも珍しい。鳥の文様は、発掘調査報告書では鳳凰の可能性が示されていたが、近年の研究では、姿形や頭部から出た一本線等から鵜ではないかと考えられている
28 鰐口(わにぐち)
所在地:神坂 金剛座寺
年代:室町時代
指定:平成6年8月1日

径34センチメートル、厚さ12.5センチメートルの青銅製。向かって右に「伊勢州宇保庄法橋寺勧進僧祖元」、左には「應永二十七年庚子十二月十二日」の銘がある。
29 西村廣休 植物園跡(にしむらひろよし しょくぶつえんあと)
所在地:相可
年代:江戸時代
指定:平成6年8月1日
相可大和屋11代西村廣休(1816~89)は、内外から集めた珍しい植物、約2,000種を邸内の成蹊園、櫪木園と名付けた植物園で栽培していた。現在は、宅地等となっているが県指定天然記念物のフウ樹やタラ葉が残されている。
30 多羅葉(たらよう)
所在地:相可
年代:
指定:平成6年8月1日
フウ樹(県指定天然記念物)とともに西村廣休が邸内の植物園で栽培した。モチノキ科の常緑高木で暖地の山地に生える。葉の表面に傷をつけると黒化し、昔は鉄筆などを使い写経をした。葉腋に淡黄緑色の小さい花を多くつけ、果実はまるく、赤く熟す。
31 金鳳蘭(きんぽうらん)
所在地:相可
年代:
指定:平成6年8月1日

西村廣休の遺愛樹の一つで、江戸時代「ブレンボーム」という名で日本へもたらされ、植物園で栽培されていた。廣休の死後、各地を転々とし、明治になり相可修教小学校の創立を記念して学校に寄贈された。現在は、多気町役場敷地内にある。
32 野呂元丈遺品(のろげんじょういひん)
所在地:波多瀬
年代:江戸時代
指定:平成7年12月12日

元禄6年(1693)波多瀬に生まれた元丈は、21歳の時親戚の医師野呂三省の養子となり、京都で儒学・本草学を学んだ。八代将軍徳川吉宗の命により、幕府の採薬師として薬草採取のために日光、箱根、富士山、白山、立山など日本全国を訪ねた。元文4年(1739)吉宗の御目見医師となった野呂元丈は、翌年青木昆陽と共に蘭学研究を命ぜられ、18世紀後半に芽生えた和蘭医方の基礎を築いた。
33 波多瀬の山桜(はたせのやまざくら)
所在地:波多瀬
年代:
指定:平成8年12月19日
※令和3年3月1日指定解除

明治36年(1903)波多瀬小学校が新築移転した際、生徒が西岡山から幼木を引いてきて植えたもの。葉は細かく楕円形で緑濃く、芽出しの際は赤みを帯び、花は葉と共に開き5弁桜色で花柄は数個ずつ散房状に並び、総状である。
34 雲版(うんぱん)
所在地:朝柄 昌慶寺
年代:桃山時代
指定:平成9年12月12日

縦56センチメートル、横52センチメートルの雲形で平たい鋳銅製・両面式で頂部が花先形、身部の左右に蕨手形の太い刳り込みがあり、撞座は八葉弁二段の蓮華を鋳出している。滋賀県の鋳物師・田中藤左衛門作。
35 五箇篠山城跡(ごかささやまじょうせき)
所在地:朝柄・古江
年代:
指定:平成9年12月22日

標高140メートル、比高差70メートルの完全な独立丘陵。城の中心は東西尾根を深い堀切りで分断して築かれた台状の連郭群と、その周囲に配した帯郭からできている。郭は土塁を伴っていないが、西端のみコの字型の土塁がある。虎口も設けられ、3メートル低い郭を経て屈折した道につながっている。この城は上野国より移り住んだ野呂一族が支配していたが、永録12年(1569)織田信長の伊勢侵略により、落城し、今に至っている。
36 紙本墨書大般若経(しほんぼくしょだいはんにゃきょう)
所在地:多気郷土資料館(井内林 光徳寺より寄託)
年代:室町時代
指定:平成10年1月30日

光徳寺の開祖玄朗和尚が、康永2年(1343)玉田寺(松阪市田村町)の上座にあったときこれを書写し、林神社に移したが、のち光徳寺(井内林)に預けられたと伝えられる。
37 大西源一関係鹿東文化歴史資料(おおにしげんいちかんけいろくとうぶんこれきししりょう)
所在地:弟国
年代:
指定:平成10年1月30日

故大西源一氏が生前収集された中世から近代に及ぶ書籍、古文書等の資料を保管する文庫。
38 真盛上人筆六字名号(しんせいしょうにんひつろくじみょうごう)
所在地:相可 浄土寺
年代:室町時代
指定:平成12年10月20日

縦76.2センチメートル、幅28.5センチメートルの紙本墨書。真盛上人は、室町時代伊勢に生まれ比叡山で修行した高僧で、西教寺を復興した天台真盛派の祖である。
39 真盛上人念仏志趣書(しんせいしょうにんねんぶつししゅしょ)
所在地:相可 浄土寺
年代:室町時代
指定:平成12年10月20日

縦127.5センチメートル、横41.8センチメートルの紙本墨書。真盛上人が、文明17年(1485)3月射和の延命寺において、六八称名会を行った際、浄土寺開祖の盛定に附与されたもの。
40 法華経八巻(ほけきょうはちかん)
所在地:相可 浄土寺
年代:室町時代
指定:平成12年10月20日

縦30.5センチメートル、長さ305センチメートル。紙本墨書。盛定の自筆。如法経とは一定の法式にしたがって経典を写すことで、その経典は主に法華経である
41 如法経縁起(にょほうきょうえんぎ)
所在地:相可 浄土寺
年代:室町時代
指定:平成12年10月20日

縦30.5センチメートル、長さ305センチメートルの紙本墨書。盛定の自筆。如法経とは一定の法式にしたがって経典を写すことで、その経典は主に法華経である。
42 現当所願之状(げんとうしょがんのじょう)
所在地:相可 浄土寺
年代:室町時代
指定:平成12年10月20日

縦28.5センチメートル、長さ126センチメートルの紙本墨書で、極楽寺(松阪市上蛸路町)への寄付を募る勧進の趣旨を書いた勧進帳である。巻末に大永2(1522)年の銘があり、檀那は相可の松屋善左衛門持冨とある。極楽寺は浄土寺と同じ、天台真盛宗であったので、のち浄土寺に移されることになったと考えられている。
43 二枚折屏風片双および二枚折屏風の写し一巻(にまいおりびょうぶかたそうおよびにまいおりびょうぶうつしいっかん)
所在地:相可 浄土寺
年代:江戸時代
指定:平成12年10月20日

高24.5センチメートル 長37センチメートル 江戸時代中期、相可の文人村田重信が元文三年(1738)6月に先の屏風の詠を解読し、筆者の略伝をのせたもの。

高165.5センチメートル 幅167センチメートル 台金地張交屏風。江戸時代中期相可へ来遊した文士ら十二卿の詠詩。
44 鰐口(わにぐち)
所在地:相可 浄土寺
年代:江戸時代
指定:平成12年10月20日

径37センチメートル、幅20センチメートルの鉄製。鰐口の銘によると、相可の旧家村田儀兵衛が慶長18年(1613)9月に、相可の見初寺に寄進したもの
45 真盛上人説法の図(しんせいしょうにんせっぽうのず)
所在地:相可 浄土寺
年代:室町時代
指定:平成12年10月20日

縦84.5センチメートル、横36.3センチメートルの絹本着色。文明17年、射和の延命寺で念仏を勤修した際の様子をうつしたものといわれている。
46 三宝荒神画像(さんぽうこうじんがぞう)
所在地:相可 浄土寺
年代:室町時代
指定:平成12年10月20日

縦86センチメートル、横34.7センチメートルの絹本着色。三宝荒神とは、不浄や災難を除去する神とされることから、火との竃の神として信仰され、かまど神として祭られることが多い。
47 立梅井堰(たちばいいせき)
所在地:松阪市飯南町
年代:
指定:平成13年5月25日
※平成30年5月30日指定解除

立梅用水は、文政6年(1823)、丹生村の地士、西村彦左衛門らの努力と紀州藩直属工事により工事費12,600余両、人夫延べ247,000余人を投じて造り上げられた農業用水である。延長が7里20町(約30キロメートル)、かんがい面積は470余町歩(約470ヘクタール)にも及ぶ。松阪市飯南町の立梅に築造された井堰は、下流の「高岩」と呼ばれる岩を砕いて石張りの堰堤にしたことから石張堰堤と言われている。堰中央より右岸側には木材を流す為の流木路も設けられ、石積みの巧みな技術とその景観は大変優れたものである。なお、かんがい時期以外、用水は中部電力株式会社波多瀬発電所の発電に利用されている。
48 目細谷築堤(めぼそだにちくてい)
所在地:朝柄
年代:
指定:平成13年5月25日

立梅用水は全線、山と平地を縫うように流れ、谷を横断するにあたっては、石積みの堤を築き、谷水も取入れている。この築堤は、40センチメートル級の谷石を用いた「乱れ空石積」であり、今も築かれたままの形を留めている。
49 エンゲ切通(えんげきりとおし)
所在地:丹生
年代:
指定:平成13年5月25日

丹生のエンゲは、片麻花崗岩でもろく崩落しやすく、また山が低いため「切通し」で用水工事が行われた。
50,51 柳谷トンネル1および2(やなぎだにとんねる)
所在地:丹生
年代:
指定:平成13年5月25日

トンネルの掘削工事の際、照明にカンテラ等を使用したとみられ、油煙で岩肌が黒くなった部分やノミを振るった跡が残っている。
52 塔ノ本トンネル(とうのもとトンネル)
所在地:丹生
指定:平成13年5月25日

トンネルの入口より29メートル付近に「水銀のたぬき掘り」と呼ばれる水銀鉱跡(斜坑)と用水がたまたま接している部分が見られる。
53 快楽園(けらくえん)
所在地:丹生 本楽寺
年代:江戸時代
指定:平成15年3月20日

文化13(1816)年、本楽寺第六代住職尼子合明により、本堂・庫裏が再建された際、本堂裏の低地を開削し南北に長い600余坪(2,000平方メートル)の回遊式庭園を築造し、快楽園と称した。
54 銅造菩薩形立像(どうぞうぼさつがたりゅうぞう)
所在地:相可
年代:奈良時代
指定:平成16年7月5日

像高11センチメートルの銅製、一鋳の菩薩像。仏体、蓮肉、蓮茎の形式、造形的な動性ともに古様をしめす。両肘をうしろに引く姿勢、上半身を反らす動きが特徴的である。火に遭ったと見られ、全身を酸化皮膜が覆い、面貌も崩れているが、白鳳早期のものと考えられる。
55 合明日記(ごうみょうにっき)
所在地:丹生 本楽寺年代:江戸時代 指定:平成16年3月23日

本楽寺6世住職尼子合明(1785~1854)が、文化12(1815)年31歳の時から嘉永7(1854)年に亡くなる半年前迄の40年間書き綴った「合明日記」9冊(総計1,794ページ)。本居春庭との交流、近隣社会の様子などが克明に記述されており、近世文化史・庶民史の好資料である。
56 親鸞聖人絵伝(しんらんしょうにんえでん)
所在地:丹生 浄福寺
年代:江戸時代
指定:平成16年3月23日

浄福寺第6世惠照は寛延2年(1749)、本堂の再建を行った。この絵はその落慶記念に高田本山第十九世圓祥上人から天保2年(1831)下付されたものである。親鸞聖人が9歳で得度してから、吉水、流罪、関東布教、帰洛、そして90歳の御入滅までを、絹本彩色4幅の掛軸に表したもの。
57 櫛田川渓流植物群落(くしだかわけいりゅうしょくぶつぐんらく)
所在地:片野
指定:平成16年3月23日

櫛田川渓流には、貴重な植物群落が発達している。低木類ではユキヤナギ(バラ科)、カワラハンノキ(カバノキ科)、キハダ等がある。草木類ではシラン(ラン科)本種の亜類であるシロバナシランも生育している。また、アワモリショウマ、ホソバコンギク、イヌトウキ、ショウスゲ、サワヒメスゲ、ナルコスゲ等がある。
58 神宮寺仁王門(じんぐうじにおうもん)
所在地:丹生 神宮寺
年代:江戸時代
指定:平成17年3月24日

「丹生大師」と親しまれている神宮寺は、宝亀5(774)年弘法大師の師、勤操大徳が創建し、弘仁年間(810年~842年)に弘法大師が七堂伽藍を建立したと伝えられている。天正年間、三瀬左京の乱等により、諸堂がことごとく焼失した。仁王門は享保元(1716)年に再建されたもので、正面に仁王像が2体、背面に多聞天、持国天が安置されている。令和元(2019)年に仁王門および仁王像2体と二天像が大修復され、建立当時の姿が蘇った。
59 千尋江神社本殿(ちひろえじんじゃほんでん)
所在地:下出江
年代:江戸時代
指定:平成17年8月22日

文永年間(1264~1275)野呂氏隆が上野国より移住するにあたり、この地に奉遷。天正年間(1573年~1592年)兵火により焼失したが、寛永17(1640)年徳川家綱の家臣である池田慶儀が再興。旧態の本殿を残している数少ない建物である。
60 北畠具房奉行人奉書(きたばたけともふさぶぎょうにんほうしょ)
所在地:丹生 智禅寺
年代:室町時代
指定:平成17年8月22日

北畠家から寄進された智禅寺の土地の保証に関する文書。北畠具房の奉行人「房兼」が永禄11(1568)年に鳥屋尾石見守満栄に宛てた書状。秘書官にあたる房兼から実務担当の満栄に、北畠氏当主の意志を間接的に伝えた奉書。
61 真盛上人画像(しんせいしょうにんがぞう)
所在地:丹生 智禅寺
年代:室町時代
指定:平成17年8月22日

縦113センチメートル横87センチメートルの絹本著色の掛軸。上人が念仏を唱える姿を表したもので、真剣さを湛えた尊貌は、細い硬めの筆線で的確に描かれている。
62 木造神像(もくぞうしんぞう)
所在地:神坂 金剛座寺
年代:平安時代
指定:平成19年1月9日

男神像。像高31センチメートルで檜の一木造り、胸前から膝もとの線で浅く削がれている。顔の細部は摩耗しており明らかではない。木肌の荒れが目立つ。両手は現在合掌しているが、もとは拱手の姿で、杓を持っていたと想定される。本堂のすぐ上に式内穴師神社跡があり、祠にご神体として祀られていた。
63 聖観音立像(しょうかんのんりゅうぞう)
所在地:四疋田 歓喜寺
年代:平安時代
指定:平成19年1月9日

内刳り(木の伸縮による亀裂を防ぐため像の内側を削り取る工夫)はわずかである。木眼は前方を直視している。なで肩で、腰をやや左にひねり、右足は軽く遊歩の姿。脚に翻波式衣文の名残がある。蓮華上に立ち、挙身光背を負っている。
64 朝鮮鐘(ちょうせんがね)
所在地:井内林 光徳寺
年代:江戸時代
指定:平成19年1月9日

高さ133センチメートル、外径73センチメートルで、和鐘のような袈裟襷がなく、琵琶を持った飛天などを浮き彫りにしたものが確認できるなど、朝鮮鐘の様式を踏襲している。
65 マメナシ(まめなし)
所在地:野中
年代:
指定:平成19年1月9日

県指定希少野性動植物種。日本の野生ナシの一種でイヌナシともいう。中国原産の落葉性の高木でよく分枝する。花期は4月、直径約25ミリメートル前後の白色の花が咲き、直径約10ミリメートルのナシによく似た実をつける。
66 神宮寺本堂(じんぐうじほんどう)
所在地:丹生 神宮寺
年代:江戸時代
指定:平成20年4月16日

延宝年間(1673~1681)に建立されたとみられる。構造形式は桁行4間、梁間3間、入母屋造り、本瓦葺き、妻入りで南面建ちである。妻の正面には一間向拝を出している。
67 神宮寺大師堂(じんぐうじたいしどう)
所在地:丹生 神宮寺
年代:江戸時代
指定:平成20年4月16日

天正18(1590)年に良心によって建立され、貞享年間(1684~1688)頃に文蕘によって再建された。構造形式は桁行3間、梁間3間、宝形造り、桟瓦葺き、南面建ちで正面に一間向拝を付けている。
68 神宮寺護摩堂(じんぐうじごまどう)
所在地:丹生 神宮寺
年代:江戸時代
指定:平成20年4月16日

宝暦13(1763)年に示寂した了泉によって建立された。構造形式は桁行3間、梁間3間、入母屋造り、本瓦葺き、妻入りで小型の仏堂となっているが、堂内は護摩壇を設けるために奥深く取り、高く広い空間を造っている。
69 神宮寺客殿(じんぐうじきゃくでん)
所在地:丹生 神宮寺
年代:江戸時代
指定:平成20年4月16日

寛永19(1642)年の天井入用覚書があり、寛永年間(1624~1644)に建立されたとみられる。構造形式は桁行長6間半、梁間長6間、入母屋造り、本瓦葺き、妻入りで南面建ちである。また、間取りは2列3室の6室構成とし更に妻入りとしたことで奥行が深く、3列目の室を加えて都合9室構成となっている。
70 近長谷寺庫裏(きんちょうこくじくり)
所在地:長谷 近長谷寺
年代:江戸時代
指定:平成20年4月16日

構造形式は桁行9間半、梁間5間半、入母屋造り、本瓦葺き、東面建ちである。外観は本堂東隣後方に建つため、本堂の正面に合わせて南側妻をみせている。間取りは北側3分の1を庫裏部分に、南側3分の2を書院部分としている。
71 珊瑚寺山門(さんごじさんもん)
所在地:五桂 珊瑚寺
年代:江戸時代
指定:平成20年6月25日

伊勢の御師福井太夫の表門を移築したもので、桁行3.5メートル梁間2.93メートル、薬医門として建ちの高い門である。蟇股、斗栱などの絵様から判断して18世紀中頃の遺構とみられる。
72 丹生水銀鉱採掘跡(日ノ谷)
所在地:丹生 日ノ谷
年代:昭和時代
指定:平成29年7月26日

現在確認されている500ヶ所近くもある水銀鉱採掘坑のうち、昭和に入ってから北村覚蔵氏が再開発を手がけた新しい採掘坑である。
73 木造十一面観音立像
所在地:五桂 珊瑚寺
年代:室町時代末から江戸時代
指定:平成30年4月6日

五桂にある珊瑚寺の本尊。町内の仏像としては、像高6.6mの近長谷寺本尊十一面観音立像に次ぐ、大きさで、3.5mを超える巨像であり、こうした大きさの像は県内にも例が少なく、貴重なものである。また、本像が近長谷寺像の影響下で制作されたことは疑いなく、当地の観音信仰を考える上でも興味深い作例である。
この記事に関するお問い合わせ先
教育課 社会教育係
電話: 0598-38-1122 ファックス: 0598-38-1130
お問い合わせフォーム


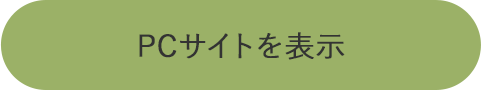
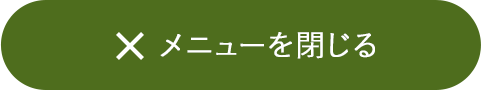
更新日:2024年04月01日