多気郷土資料館企画展(春季)とミニ展示
企画展「くらしの形と心 vol.1 ~調理する~」
道具や文書など、目に見える形から、先人たちがどのように暮らしてきたのかを探り、それらを生み出し、また利用してきた人々の心に迫ろうというシリーズ企画展を今回よりはじめます。第1回は「調理する」をテーマに取り上げます。
「簡単、早い、おいしい」を求める人々によって改良工夫が加えられ、進化してきた調理道具。食の探究が新しい道具、調理法を生み出し、現在のように、バラエティ豊かな食をもたらしました。
食物の調理に使われた道具をはじめ、昔の料理レシピや献立が掲載された文書や書籍等も展示します。
この展示を通して、先人の暮らしぶりを知り、食嗜好や食生活の変化を感じ取っていただければと思います。

木製 角せいろ

焙烙皿
ミニ展示「埋もれていたモノたち 森荘川浦遺跡1」
長い間、日の目を見ることのなかった館蔵の出土品を、一つの展示ケースだけで年に1回、順次、紹介します。
今回は森荘川浦遺跡の出土品のうち、土器などの土製品を展示します。同遺跡は、多気町森荘字川浦にあります。県内の縄文遺跡のなかでは、戦後早い時期に多量の石鏃や剥片の散布地として知られていました。平成6年6月から9月に行われた発掘調査で出土した遺物の一部を紹介します。

森荘川浦遺跡出土 縄文土器片

森荘川浦遺跡出土 土偶片
展示期間
令和7年5月9日(金曜日)~6月22日(日曜日)
場所
多気町多気郷土資料館(多気町相可1620 多気郡教育会館1階)
開館時間
午前9時から午後4時まで
休館日
月曜・祝日
入館料
無料
お問い合わせ先
多気郷土資料館 0598-38-1132
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


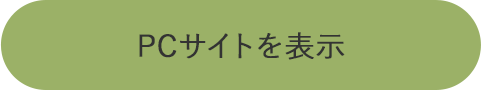
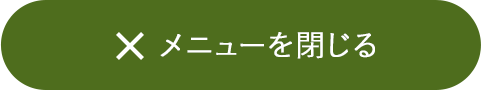
更新日:2025年04月22日