「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について 【準備中】
令和6年分の所得税実績額が確定した結果、令和6年度に実施した調整給付(当初給付分)の給付額に不足が生じる場合等には、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施予定です。
現在、給付対象者の確認及び給付額の算定を行っており、現時点では「不足額給付の対象者になるか」「給付額がいくらになるか」などの個別のお問い合わせに回答することはできません。
対象となる方には、8月下旬から順次個別に通知を行うよう準備をしておりますので、通知がお手元に届くまで今しばらくお待ちください。
ご迷惑をお掛けしておりますが、ご了承ください。
詳細が決まり次第、このホームページや広報紙等でお知らせいたします。
なお、個人情報保護のため電話ではお答えできない内容もございますので、あらかじめご了承ください。
支給対象者
令和7年1月1日現在において多気町に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方に支給されます。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
ただし、次の世帯は今回の給付金の対象となりません。
1)すでに多気町以外の市区町村から同様の重点支援給付金を受けている世帯かその世帯の世帯主を含む世帯、世帯員のみで構成される世帯。
2)租税条約による免除の適用の届出により住民税の免除を受けている者を含む世帯。
不足額給付1
当初調整給付の算定では、令和5年分所得等をもとにした推計値(令和6年分推計所得税)を用いて算定しました。そのため、年末調整や、確定申告などにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額(表のA)と、当初調整給付額(表のB)との間で不足の差額が生じた方に対して、その差額(表のC)を支給します。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と、令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)の方は対象ではありません。

<対象者例A>
・令和6年中に退職や休職など令和5年分所得に比べて、令和6年分所得が減少したことにより、令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方。

<対象者例B>
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった方。

<対象者例C>
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が変更し、本来給付されるべき額が発生した方。

<対象者例D>
・学生の就職等で、令和5年中の所得がなく、令和6年中所得がある方。

不足額給付2
★次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
1)所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前が0円)→本人として定額減税対象外である方
2)扶養親族としても定額減税の対象外である方(税制度上「扶養親族」の対象外)→青色事業専従者・事業専従者(白色)〈例1〉や、合計所得金額48万円を超える方〈例2〉
3)低所得世帯向け給付金(※)の対象になっていない方(低所得者世帯向け給付対象者世帯の世帯主・世帯員でない)
※以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)


よくあるお問い合わせ
〇不足額給付とは
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計値(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた方に対して、その不足分を1万円単位で切り上げて給付するものです。
支給対象となりうる方の例
・令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
・令和6年中に、扶養親族等が増加した方
・当初調整給付後の税額修正により、令和6年度個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じた方
【不足額給付2】
不足額給付1とは別に、次のすべての要件を満たす方について原則定額4万円を給付するものです。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
要件
・本人として定額減税対象外であること。
→令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ。
・扶養親族として定額減税対象外であること。(税制度上、「扶養親族」の対象外)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方。
・低所得者世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当してないこと。
※1
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
〇多気町から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
令和7年1月1日時点での住民登録地が多気町である場合は多気町から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
〇昨年に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることができますか。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となることはあります。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
〇令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族が増加しましたが、不足額給付の対象になりますか。
こどもが生まれた等で扶養親族の数が増えたことにより、令和6年の夏頃に実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。また、不足額給付の取り扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。
・個人住民税
令和5年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、令和6年中に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、対象となりません。個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
・所得税
令和6年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、年末調整または確定申告書により、所得税から引ききれない金額が出た場合は、不足額として追加で給付する予定となります。
〇令和6年度個人住民税は非課税であり、非課税世帯等の給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか。
令和6年度非課税世帯への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。非課税世帯等給付金を返還する必要はありません。
〇令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていましたが、この額が給付されるのでしょうか。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない例)
・すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付されている。
・確定申告などで所得税額が源泉徴収票と異なる場合。
・源泉徴収票以外に収入がある場合。 など
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


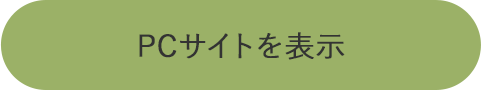
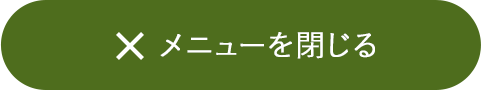
更新日:2025年06月20日